介護保険料
介護保険料とは?
介護保険制度は、国や都道府県、市町村が負担する公費(税金)と、皆様から納めていただく介護保険料を財源として運営されています。
財源の負担割合
介護保険の財源の負担割合は、全体の半分の額を公費(税金)で、残りの半分を第1号被保険者(65歳以上)の方と第2号被保険者(40~64歳)の方で出し合うことになっています。
保険料の所得段階について、国の示す標準段階が9段階から13段階に変更となったため、本町においても令和6年度から所得段階を13段階に変更しております。
|
段階 |
対象者 |
割合 |
保険料年額 |
保険料月額 |
|---|---|---|---|---|
|
第1段階 |
|
0.285 |
18,468円 |
1,539円 |
|
第2段階 |
世帯全員が町民税非課税で、本人の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が120万円以下の方(第1段階に該当しない方) |
0.485 |
31,428円 |
2,619円 |
|
第3段階 |
世帯全員が町民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない方 |
0.685 |
44,388円 |
3,699円 |
|
第4段階 |
本人が町民税非課税で、世帯の中に町民税課税者が含まれており、本人の課税年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万9千円以下の方 |
0.90 |
58,320円 |
4,860円 |
|
第5段階(基準額) |
本人が町民税非課税で、世帯の中に町民税課税者が含まれている方(第4段階に該当しない方) |
1.00 |
64,800円 |
5,400円 |
|
第6段階 |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
1.20 |
77,760円 |
6,480円 |
|
第7段階 |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
1.30 |
84,240円 |
7,020円 |
|
第8段階 |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
1.50 |
97,200円 |
8,100円 |
|
第9段階 |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
1.70 |
110,160円 |
9,180円 |
|
第10段階(新設) |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
1.90 |
123,120円 |
10,260円 |
|
第11段階(新設) |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
2.10 |
136,080円 |
11,340円 |
|
第12段階(新設) |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
2.30 |
149,040円 |
12,420円 |
|
第13段階(新設) |
本人が町民税課税者で、前年の合計所得金額が720万円以上の方 |
2.40 |
155,520円 |
12,960円 |
保険料の年額は、(基準額の月額5,400円×各段階の割合)×12ヵ月で算定しています。
介護保険料の納め方
- 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方
→(特別徴収)年金からの天引きとなります - 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金が年額18万円未満の方
→(普通徴収)納付書や口座振替で納めることになります
(注)普通徴収の納付書に印刷されているバーコードを読み取ることでスマートフォンでの決済も可能です。
その他、次の場合は普通徴収になります。
- 年度の途中で他市町村から転入したとき
- 年度の途中で所得段階区分に変更があったとき
- 年度の初め(4月1日)の時点で年金を受給していないとき
- 年度途中で介護保険料が変更になったとき
- 1回の年金支給額の半分の額が、介護保険料天引き額を下回ったとき
- その他(年金の一部のみを受給している時など)
徴収方法について
前半4・6月には前年度2月分の保険料と同額を徴収(仮徴収)し、後半8・10・12・翌年2月には確定後の保険料から仮徴収分を除いた額を振り分けて徴収(本徴収)します。
※特別徴収の方は8月までが仮徴収、10月からが本徴収となります。
令和7年度介護保険料本算定用チラシ (PDFファイル: 250.0KB)
- 年度途中に亡くなられた方や転出された方は、その前月分までの月割で精算します。
- 65歳になった方、転入した方は、月割りで計算します。
- 65歳になった方は、65歳の誕生日の前日のある月から納めます。
例)8月1日生まれの方→7月分から 8月2日生まれの方→8月分から
介護保険料を滞納した場合
特別な事情がないのに保険料を滞納していると、サービスを利用する際に、次のような措置がとられる場合があります。
利用者がいったんサービスの全額を負担し、その後申請により保険給付分が払い戻されたり、償還払いにより支給される金額から、滞納している保険料の額を差し引くことがあります。
また、利用者の負担が1割から4割に引き上げられるなどの措置がとられます。
保険料の減免等
災害等により住宅や家財について著しい損害を受けた方などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられる場合がありますので、ご相談ください。
第2号被保険者の保険料(40歳から64歳まで)
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料に加算されています。加算されている介護保険料の額や計算方法は加入している医療保険によって異なります。
たとえば64歳の人の場合、第2号被保険者としての加入期間は、65歳の誕生日の前々日までとなります。
国民健康保険に加入している場合
- 国民健康保険税に含めて介護保険料を算定します。
- 世帯ごとに世帯主が納めます。
職場の医療保険(健康保険や共済組合など)に加入している場合
給与(標準報酬月額)および賞与に介護保険料率をかけて介護保険料を算定します。
(注)加入している医療保険によって介護保険料率は異なります。加入している医療保険者(国民健康保険や職場の医療保険)におたずねください。
確定申告における社会保険料控除の対象
前年中に支払われた介護保険料は、お勤め先の健康保険料や国民健康保険税、国民年金保険料と同様に、社会保険料控除の対象になります。年末調整や確定申告の際に計算に含めてください。支払額は領収書でご確認ください。
(注)特別徴収(年金天引)の方につきましては、毎年1月下旬に日本年金機構等から送付される公的年金の源泉徴収票に記載されます。ただし、特別徴収で納付した介護保険料を社会保険料控除として利用できるのは、年金受給者本人のみに限られますのでご注意ください。
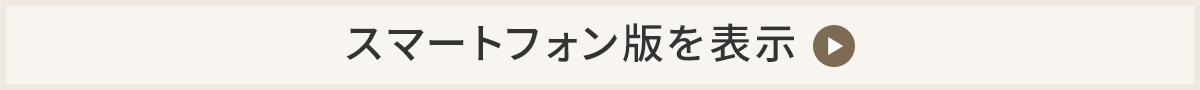





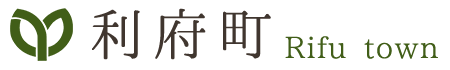
更新日:2024年05月10日