郷楽遺跡
郷楽遺跡は、三陸自動車道建設工事に伴い行った発掘から計6回に渡り調査が行われています。
その調査の結果、古墳時代(6-7世紀頃)に造られたと考えられる4基の円墳や、奈良~平安時代(8-10世紀頃)に建てられたと考えられる住居跡も多数発見されました。
朝顔形埴輪

復元された朝顔型埴輪(町指定文化財)
郷楽遺跡からは宮城県内でも発見数が少ない「朝顔形埴輪」が見つかっています。
古墳時代の「埴輪」はほとんどが「円筒埴輪」と呼ばれる筒状の物で、古墳の頂上部分に並べて設置されました。
なかでも「朝顔形埴輪」は並べられた「円筒埴輪」の要所に設置されていたと考えられています。
郷楽遺跡から出土した「朝顔形埴輪」は特に保存状態が良好な事から町指定文化財に指定されています。

利府町郷土資料館公式キャラクター
「あさガオー」のモデルにもなりました。
時代を超えて広がる住居跡
郷楽遺跡では、前述のとおり古墳時代(6-7世紀頃)から奈良、平安時代(8-10世紀頃)に渡って多くの遺構が残されています。
古墳が造られていた6-7世紀のものだけでなく、8-10世紀(奈良~平安時代)に建設されたと考えられる建物跡が多く発見されました。

見つかった竪穴住居跡
8-10世紀頃には、郷楽遺跡の主体をなす遺跡群が形成された時期で、住居が連続して建てられた時代だと考えられています。

竪穴住居の復元イメージ
郷楽遺跡では、掘立柱建物跡(ほったてばしらたてものあと)も見つかっています。
奈良~平安時代にかけては竪穴住居が一般的な住居として知られていて、掘立柱住居は多賀城政庁など、地位や身分の高い人が住んだ地域で発見されており、郷楽遺跡にも当時多賀城政庁と関係のある相応の身分の方が住んでいたものと考えられています。
他にも多賀城政庁で使用されていたものと同じ刻印がある瓦や当時の利府では生産されていないはずの軒丸瓦が発見されるなど、多賀城政庁と深い関わりのある遺跡であることがうかがえます。

見つかった掘立柱建物跡。当時の建築物としては珍しい発見でした。


竈の暗渠水路から見つかった瓦。
それぞれ刻印が施されていて、同じ特徴を持つ物は多賀城政庁と仙台市の小田原窯跡群以外に発見されていないため、関連するものと考えられています。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 生涯学習課 文化振興・リフノス係
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
電話番号:022-767-2197 ファックス番号:022-767-2108
お問い合わせフォームはこちら
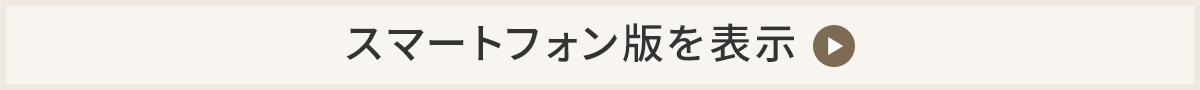






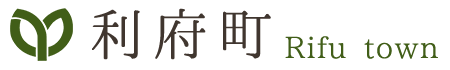
更新日:2025年03月24日