固定資産税
固定資産税とは?
固定資産税は、賦課期日に、利府町内に固定資産を所有している方(納税義務者)が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める町税です。
賦課期日と納税義務者
賦課期日
税金がかかる基準となる日のことで、毎年1月1日となります。
納税義務者
賦課期日に固定資産を所有している方です。具体的には、次のとおりです。
| 資産の種類 | 納税義務者 |
| 土地 | 土地の登記簿または土地補充課税台帳に登記または登録されている方 |
| 家屋 | 建物の登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている方 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に登録されている方 |
売買などによって実際の所有者を変更していても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日時点において完了していない場合には、1月1日時点に登記簿等に登録されている方が納税義務者となります。
固定資産の種類
- 土地
- 家屋
- 償却資産(詳細は次のとおりです。)
償却資産の主な内容
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために使用している構築物、機械・器具・備品等をいいます。
| 資産の種類 | 資産の名称 |
| 構築物 | 内部造作(内装)、舗装路面、広告塔等 |
| 機械及び装置 | 旋盤、製品製造設備、ポンプ等 |
| 船舶 | 漁船、ボート等 |
| 車両及び運搬具 | 構内運搬車、フォークリフト等(自動車税や軽自動車税の課税対象車を除く) |
| 工具器具及び備品 | 取付工具、金庫、テレビ等 |
- 取得金額が20万円(ただし、平成元年3月31日以前取得の場合は10万円)以上のものが該当になります。
なお、耐用年数が1年未満の資産は対象になりません。 - 耐用年数を経過し、減価償却が終わった資産についても、その資産が事業のために使うことができる状態にあるかぎり、対象となります。
次のようなものが、対象となる資産の一例です。
| 業種 | 資産の名称 |
| 事務所 | 応接セット、ロッカー、エアコン、所内内装等 |
| 小売店 | 看板、陳列棚、レジスター、自動販売機等 |
| 飲食店 | カラオケセット、冷蔵庫、接客用家具等 |
| 理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備等 |
| 病院 | 各種医療機器、キャビネット等 |
| アパート | 駐車場アスファルト舗装、自転車置き場、外構フェンス等 |
| 駐車場事業 | 柵、舗装路面等 |
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
- 割賦販売による資産は、買主の方が申告してください。
- リース資産は、賃貸人の方が申告してください。
- テナントに施した内装等については、原則として賃借人の方が申告してください。
- 初めての申告となる場合、申告書の送付は行いませんので、1月31日までに必要書類に記載のうえ、税務課資産税係あて申告してください。
固定資産の評価額の決め方
固定資産の課税の基礎となる評価額は、一定の基準により適正な時価を求める方法によって決定しています。
評価額は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に決定されます。この評価を替える年を基準年度(最近では令和6年度)といいます。しかし、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変更や家屋の新築または増築があった場合には、新たに評価を行い、資産の状況に応じた評価額を決定しています。
| 資産の種類 | 評価方法 |
| 土地 | 固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価額を基礎として評価 |
| 家屋 | 再建築価格を基礎として評価 |
| 償却資産 | 取得価格を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価 |
税額の算出方法と税額
課税標準額×税率(1.4%)
基本的には、「評価額=課税標準額(税金をかける基準となる額)」となりますが、課税標準の特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
主な特例措置については、「固定資産税の特例・減額措置」のページをご覧ください。
なお、現在都市計画税は課税しておりません。
納税の方法
納税通知書を納税者へ送付しますので、5月、7月、9月、12月の4回の納期に納付書又は口座振替で納付いただきます。
支払い方法は以下からお選びいただけます。
・全国の金融機関窓口納付
(地方税共同機構が収納事務を委託する金融機関のみ)
・ダイレクト納付(口座振替)
・クレジットカード納付
・アプリ納付(スマートフォン決済)
詳しくは「納付について」をご確認ください。
免税点
同一人が利府町内に所有している固定資産の課税標準額の合計が下の表の場合には、固定資産税はかかりません。
| 資産の種類 | 課税標準額 |
| 土地 | 30万円未満 |
| 家屋 | 20万円未満 |
| 償却資産 | 150万円未満 |
固定資産の課税についての情報開示
固定資産税についての情報開示制度があります。
閲覧制度
固定資産を所有する方は、自己の固定資産課税台帳(土地、家屋及び償却資産に関する評価額、税額の基礎となる課税標準額等が記載されているもの)を閲覧することができます。閲覧を代理人に依頼する場合は、委任状が必要になります。
また、借地人・借家人の方は、借地・借家の資産の課税内容を確認することができます。借地・借家人の方が閲覧する場合は、賃貸借関係がわかる契約書等が必要になります。
| 閲覧できる方 | 土地・家屋の所有者及び借地人・借家人 |
| 閲覧の時期 | 毎年4月1日から随時 |
| 閲覧の場所 | 税務課資産税係 |
| 閲覧手数料 | 200円(毎年4月1日から5月31日までは無料) |
縦覧制度
自己の土地又は家屋の評価が、適正かつ公平に評価されているかどうかを確認することができるよう、土地又は家屋の評価額を記載した帳簿(土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿)を縦覧することができます。自分の資産以外に他の資産の価格等も確認できる制度です。
| 縦覧できる方 | 利府町に土地又は家屋をお持ちの方 |
| 縦覧の期間 | 毎年4月1日から5月31日まで |
| 縦覧の場所 | 税務課資産税係 |
| 縦覧手数料 | 無料 |
評価額等に不服がある場合
固定資産税の納税義務者は、当該年度の固定資産税課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、毎年4月1日から納税通知書の交付を受けた日以後3か月までの期間に、利府町固定資産評価審査委員会(事務局:利府町総務課)に対し、審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度(評価替の年度)以外の年度においては、土地の地目の変更や家屋の新築、増改築等の事情がある場合を除き、審査の申出をすることはできません。
固定資産についての各種届出
- 相続人代表者指定届出書
所有者が死亡した場合に届出願います。 - 家屋異動届出書
未登記の家屋の所有者が変更になった場合に届出願います。 - 住所地(所在地)名称等変更届出書
所有者の住所・名称が変更になった場合に届出願います。 - 家屋滅失届出書
未登記の家屋を取り壊したときに届出願います。 - 納税管理人申告書
納税管理人を選任、変更する場合に届出願います。
(注)上記の様式は税務課資産税係窓口に備え付けております。
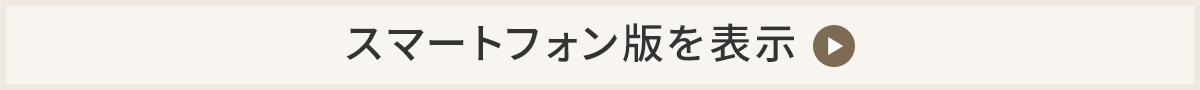





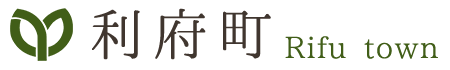
更新日:2025年09月03日