国民健康保険の制度について
国民健康保険について
日本では、病気やけがをした場合に安心して医療を受けられるよう全ての方が何らかの医療制度に加入し、保険料(税)を負担し合うことが義務付けられています(国民皆保険制度)。
国民健康保険(国保)は、他の医療制度に加入していない全ての人が加入対象となり、国民皆保険制度の根幹を支えています。
国保に加入中の方は、定年退職により他の健康保険をやめてから加入する方が多いことから、他の健康保険に比べて加入者の年齢構成が高いため、必然的に医療機関等を受診する機会も多くなります。
近年は、医療の高度化や被保険者の高齢化などの影響により一人当たりに要する医療費の増加が顕著であり、国保の財政状況は年々厳しさを増しております。
国保における医療費の支払いについては、被保険者の皆様にお支払いいただいた保険料(税)や他の医療保険制度からの負担金などが財源になります。
町では、医療費の適正化を図るため、特定健康診査をはじめとする保健事業を実施することにより、被保険者の皆様の健康の保持や疾病の重症化予防に努めておりますので、ぜひご参加ください。
被保険者の皆様が今後も安心して医療が受けられるよう、より一層の財政安定化に努めてまいります。
被保険者の皆様におかれましてもバランスの取れた食生活や適度な運動など日頃から健康管理に努めていただきますようお願いいたします。
国保の財政状況など(令和元年度から) (PDFファイル: 88.4KB)
利府町国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康診査等実施計画について
加入や脱退する場合は届出が必要です
会社などの職場の健康保険(健康保険組合・共済組合など)に加入している方、生活保護を受けている方を除いて、すべての方が国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入しなければなりません。会社などを退職して職場の健康保険をやめた場合や、利府町に転入してきた場合(一定の条件を満たしている外国の方を含む)は国保への加入の手続きが必要になります。また、国保に加入している方が他の健康保険に加入したり、他市町村へ転出する場合は、国保の脱退の手続きをしてください。これらの手続きは、原則として14日以内に行うことと規定されています。
なお、手続きの際は、世帯主と加入される方(又は脱退される方)の個人番号(マイナンバー)のわかるもの、手続きに来庁される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のほか手続内容に応じて以下の物を持参してください。
※別世帯の方が手続きに来る場合は、委任状が必要です。
|
こんなとき |
持参するもの |
|---|---|
|
他の市区町村から転入したとき |
転出証明書 (事前に利府町へ転入手続を行ってください) |
|
他の健康保険を脱退したとき |
健康保険の資格を喪失したことが確認できる書類 |
|
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
| 子どもが生まれたとき | 出生届、母子手帳 |
|
こんなとき |
持参するもの |
|---|---|
|
他の健康保険などに入ったとき |
以下のいずれかの書類 ・資格情報のお知らせ ・資格確認書 |
|
亡くなられたとき |
葬儀を行っている場合(喪主の通帳、葬儀を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、日程表など)) |
|
生活保護を受けるとき |
保護開始決定通知書 |
郵送での脱退手続きについて
窓口での脱退手続きが難しい場合は、以下の書類を町民課国保年金係へ送付していただければ、郵送での手続きが可能です。
【国民健康保険脱退手続きに必要となる書類】
・国民健康保険異動届(国民健康保険異動届(PDFファイル:332.7KB))
・新しい保険へ加入したことが確認できる書類の写し(「資格情報のお知らせ」など。やめる方全員分)
・ご本人であることが確認できる書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
【郵送先】
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府字新並松4番地
利府町 町民課 国保年金係
|
こんなとき |
持参するもの |
|---|---|
|
住所、氏名、世帯主などが変わったとき |
変更になったことを確認できる書類 |
|
就学のため、子どもが他の市町村に住むとき |
在学証明書 |
各種保険給付
医療給付
|
年齢 |
自己負担割合 |
|---|---|
|
義務教育就学前 |
2割負担 |
|
義務教育就学から70歳未満の方 |
3割負担 |
|
70歳以上の方 ※1日生まれの方は誕生月から該当。 ※1日生まれ以外の方は誕生月の翌月から該当。 |
2割負担 (世帯主又は加入者が現役並み所得者の場合は、3割負担) |
(注)0歳から18歳(18歳到達の年度末)までの方には、子ども医療費助成制度があります。
高額療養費
高額療養費制度とは、同月内に医療機関の窓口で負担した分の医療費が高額になった場合、世帯の限度額を超えた分が支給される制度です。以下の限度額は、保険適用分の医療費のみの金額で、入院したときの食事代や個室の差額室料などは含まれませんので、ご注意ください。
高額療養費に該当となった方には、通常、医療機関を受診した3か月から4か月後に世帯主様宛に申請書を送付しますので、申請書が届いてから町民課国保年金係に申請いただくようお願いいたします。
高額療養費の申請手続の簡素化について
令和5年4月以降の高額療養費の申請については、申請者から新たに高額療養費が発生した場合の申請を簡素化することを申出していただいた場合は、次回以降の高額療養費の手続が不要となり、初回に申請した口座へ自動的に振り込むことが可能となります(以下「自動振込」といいます)。自動振込ができるのは、申請時点において国民健康保険税を滞納していない世帯に限ります。また、次の事項に該当した場合は自動振込が停止され、停止後に高額療養費が発生した場合は改めて申請が必要になります。
〇国民健康保険税に滞納が発生した場合
〇世帯主が(死亡等により)変更になった場合
〇国民健康保険の資格を喪失した場合
〇申請書に記載の口座に振り込みができなくなった場合

申請に必要なもの
- 申請書(役場から郵送します)
- 世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの
- 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
70歳未満の方の場合
同月内に同医療機関等(入院・外来や医科・歯科などは別々に計算します。)での自己負担額が21,000円以上の支払いをした医療費が高額療養費の計算対象となり、その合算額が下記の自己負担限度額を超えた場合、超えた分が申請により支給されます。
|
所得区分 |
限度額 |
|---|---|
|
所得(注2)が901万円を超える…ア |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
|
所得が600万円を超え901万円以下…イ |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
所得が210万円を超え600万円以下…ウ |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)…エ |
57,600円<44,400円> |
|
住民税非課税世帯…オ |
35,400円<24,600円> |
- (注1) 過去12か以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費に3回該当した場合、4回目以降は<>内の限度額となります。
外来+入院(世帯単位)の限度額は、同じ世帯で、同じ健康保険である場合の合計額で算出します。 - (注2)所得とは、国民健康保険税の算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
70歳以上75歳未満の方の場合
70歳以上の方は、金額にかかわらず保険適用分で支払いをした医療費が計算の対象となります。外来分は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
|
所得区分 |
個人単位 |
世帯単位 |
|---|---|---|
|
現役並み所得者3 年収1,160万円~ |
252,600円+総医療費-842,000円)×1% |
252,600円+総医療費-842,000円)×1% |
|
現役並み所得者2 年収770万円~1,160万円 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
|
現役並み所得者1 年収370万円~770万円 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
|
一般(住民税課税者) |
18,000円 |
57,600円 |
|
低所得2 (低所得1.以外の方) |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得1 (年金収入の場合、受給額80万円以下の方等) |
8,000円 |
15,000円 |
(注) 過去12か以内に、外来+入院(世帯単位)の高額療養費に3回該当した場合、4回目以降は<>内の限度額となります。外来+入院(世帯単位)の限度額は、同じ世帯で、同じ健康保険である場合の合計額で算出します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証
入院する場合などあらかじめ医療費が高額になることが分かっている場合、70歳以上の低所得1、低所得2、現役1、現役2、70歳未満の方は、限度額適用認定証(住民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請をし、医療機関の窓口で認定証を保険証と一緒に提示することにより、自己負担限度額は上の表の金額までとなります。
70歳以上の一般と現役3.の方は、保険証の提示のみで、上の表の限度額が適用されます。
申請に必要なもの
- 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
※マイナ保険証を利用すれば、限度額認定証を発行しなくても限度額を超える支払いは不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

出産育児一時金
原則として、6か月以上国保に加入している被保険者が出産したときは、1人につき488,000円の出産育児一時金が支給されます。産科医療補償制度加入の医療機関で出産した場合は、12,000円が加算されます。
直接支払制度(注釈)を利用される場合は、医療機関で手続きが必要となります。詳しくは医療機関へお問い合わせください。また、直接支払制度を利用された方で、支給金額が一時金額に満たない場合は、その差額を申請することができます。
(注釈)直接支払制度:出産された医療機関に対して保険者が直接、出産育児一時金を支払う制度です。これにより、被保険者が医療機関等の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ 多額の出産費用を用意しなくて済みます。
申請に必要なもの
- 出産費用の領収証(差額の申請の場合は、医療機関が代理受領した金額のわかる分娩費用明細書等)
- 世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

葬祭費
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行なった人(喪主)に対して葬祭費50,000円が支給されます。
申請に必要なもの
- 喪主の方が葬祭を行ったことが確認できるもの(会葬礼状、日程表等)
- 喪主の名義の振込先口座番号のわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
移送費
「病気」や「けが」などによって移動をすることが困難な方が、医師の指示により移動が必要となった際の費用を保険者が必要と認める範囲で支給します(退院の際の移動や自己都合による転院などの際の移動は認められません)。
申請に必要なもの
- 領収証
- 医師の意見書
- 世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの
- 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
療養費の支給
次の場合、かかった医療費はいったん全額自己負担(10割負担)になりますが、保険者へ申請して認められると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
- 事故や旅先で急病となったため、緊急的に保険証を持たずに治療を受けたとき(治療内容の詳細が確認できる書類が必要)
- 整骨院や接骨院での施術(柔整)、はりきゅう、あんま・マッサージなどの施術を受けたとき(医師から治療の同意を得ることが必要。)
- 生血を輸血したとき(医師の輸血証明書が必要)
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの治療用装具(補装具。医師の診断者又は装着指示書が必要)
- 海外で急病などによりやむを得ず診療を受けたとき(治療目的の渡航は対象外。領収書や治療内容のわかる書類の原本に加えて、日本語に翻訳した書類も併せて必要。)
申請に必要なもの
- 領収証
- 世帯主名義の振込先口座番号のわかるもの
- 世帯主と該当者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
柔整、はりきゅう、マッサージ等の施術を受けられる方へ
単なる肩こりや筋肉疲労、疲労回復などを目的とした施術は、保険診療の対象とはなりません。保険診療による施術の場合は、あらかじめ医師の発行した同意書や診断書が必要になりますので、施術を受ける前にご確認ください。


第三者行為の届出
治療を受ける場合は届出が必要です
交通事故など、第三者の行為によってけがをしたとき場合でも国民健康保険証を使用し治療を受けることができますが、その場合、「第三者行為による傷病届」の届出が必要です。この届出は、加害者との示談を済ませる前に必ず提出してください。

医療費は加害者に請求します
第三者の行為でケガをしたときなどの医療費は、本来加害者が負担すべきものです。しかし、その損害賠償請求に時間がかかる場合がありますので、そのときには、「第三者行為による傷病届」の届出をしていただくことにより、国民健康保険で医療費を一時的に立て替えし、あとからかかった医療費の範囲で保険者が加害者等に請求することになります。
届出に必要なもの
- 第三者行為による傷病届等一式(申請書ダウンロードセンターより出力可能です)
- 交通事故証明書
- 運転免許証など本人確認ができる書類
(注)その他必要により提出をお願いする書類があります。
交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に係る覚書様式(保険会社作成用)
国民健康保険税及び一部負担金の減免又は徴収猶予について
災害や失業等により収入が著しく減少した場合で、国民健康保険税や医療機関等での診療に対する費用(一部負担金)を支払うことが困難な場合は、申請することにより国民健康保険税や一部負担金の減免又は徴収猶予が受けられます。詳細につきましては、お問い合わせください。
| 区分 | 区分2 | 条件 |
|---|---|---|
| 1 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けた方 | 共通 | 震災、風水害、火災等の災害による資産の損害割合が10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が1,000万円以下であること。 |
| 2 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少した方 | 共通 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁などによって受けた被害の額が平年の収入に対して10分の3以上であり、世帯の前年度の合計所得金額が1,000万円以下であること。 |
| 3 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した方 | 一部負担金 | 事業又は業務の休廃止、失業等により療養期間中の収入見込額が療養開始直前の6月における収入に比べて10分の3以上の減少が見込まれ、かつ、療養期間における平均実収入月額が一部負担金平均月額と厚生労働省告示の生活保護基準額の100分の110の合計より少ないと見込まれるものであること。 |
| 同上 | 国保税 | 前年の合計所得金額が500万円以下の納税義務者等で事業の廃止、失業その他の事由により当該年の合計所得見込額が前年の2分の1以下に減少し、かつ、生活が著しく困難であること。 |
- (注1)審査のため、世帯全員の所得照会や資産・預貯金等の調査をする場合もありますのでご了承ください。
- (注2)この制度を受けようとする方は、病院に行く前に必ずご相談ください。
無料低額診療事業について
経済的な理由により医療機関等を受診することが制限されることのないよう、社会福祉法に基づき一部負担金の全額又は一部の免除を受けられる制度があります。対象となる医療機関等については、宮城県のホームページにてご確認ください。
宮城県ホームページhttps://www.pref.miyagi.jp/documents/28844/763547.pdf
セルフメディケーション税制について
セルフメディケーションとは、自分自身で健康を管理し、軽度な身体の不調を自分で市販の医薬品等を用いて手当てすることです。保険証を使用せずに治療を行うため、医療費の削減にもつながりますので、積極的にご利用ください。
健康の保持増進や疾病の予防のために定期健康診断の受診やがん検診の受診など一定の取り組みを行っている方が、年12,000円以上の対象医薬品(スイッチOTC医薬品(薬局・薬店・ドラックストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品))を購入した場合に所得控除を受けることができます。詳細は、厚生労働省のホームページ等にてご確認ください。
令和6年12月2日以降は、健康保険証は発行していません。
国の方針により、現行の保険証の発行は令和6年12月1日までとなっています。現在は、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することとなります。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると以下のとおり様々なメリットがあります。マイナンバーカードをお持ちでない方につきましては、マイナンバーカードの取得と健康保険証への紐づけを積極的にご検討ください。詳細はデジタル庁のホームページ等にてご確認ください。
〇よりよい医療の提供が可能になります!
本人が同意すれば、これまでの健診や医療情報等が共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
〇限度額認定証としても利用可能!限度額認定証の申請が不要になります。
〇マイナポータルを活用してより便利に!
マイナポータルから本人の特定健診情報を閲覧できるほか、所得税の医療費控除の手続でマイナポータルを通じて自動入力できるようになりました。
※マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付しますので、資格確認書を医療機関等に提示することにより、引き続き医療を受けることができます。
マイナ保険証(R7.2現在) (PDFファイル: 1.9MB)
お薬手帳を活用しましょう!
「いつ」「どこで」「どんな」薬を処方されたかを記録しておく手帳です。記録しておくことで複数の医療機関を受診する際などに、服用しているお薬の情報を共有できます。
お薬手帳を持たずに複数の医療機関を受診すると同じ作用の薬が重複して処方されてしまう場合があります。重複分の薬代を余計に支払ってしまうだけではなく、必要以上の量を服用することによって健康被害が発生することが懸念されます。
また、複数の薬を飲み合わせることによって健康被害を及ぼす危険があるため、複数の薬を服用する際は専門家による管理が必要になります。
※かかりつけ薬局(複数の処方箋を一つの薬局にまとめて薬の処方を受けること)を持つことによって、お薬手帳を持つことと同等の効果を得ることができます。
健康ポイント事業にご参加ください!
利府町国民健康保険に加入している方が特定健康診査や各種がん検診、健康教室などに参加し、一定の健康ポイントをためて応募していただいた方に記念品を贈呈しております。ご自身の健康維持増進を進めるとともにポイントで記念品を獲得してみませんか。
〇対象者
利府町国民健康保険被保険に加入している方
〇ポイント対象事業
特定健康診査、がん検診等の各種検診、健康教室への参加など
〇参加方法
別添チラシをご確認ください。
(毎年6月頃に発送している各種健診等申込書にも同封しております)
R7国保健康ポイントチラシ (PDFファイル: 874.7KB)
リフィル処方箋について
病気等の症状が安定している患者さんについては、医師と薬剤師の連携の元、医師の判断により、一定期間内に処方箋を繰り返し使用できるようになりました。患者さんにとっては医療機関を受診する回数を減らすことが可能となり、通院に要する費用等が抑えられることとなります。ご自身の症状が該当するかどうかお医者さんにご相談ください。
※新薬など一部対象外となる薬もあります。
宮城県健康増進アプリ(kencom)について
令和7年3月12日から宮城県の市町村国民健康保険に加入する満18歳以上を対象に健康増進アプリの運用が開始されました。ご自身の健診結果の閲覧、歩数や血圧などのライフログ、健康増進情報の配信等の機能を使うことができます。日々の健康を維持するため、アプリをぜひ活用してみてください。詳細については別添チラシをご確認ください。
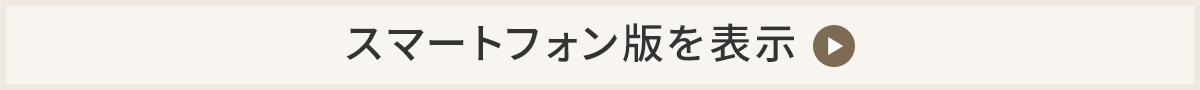






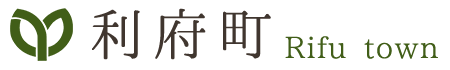
更新日:2026年02月18日