固定資産税の特例・減額措置
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)については、その住宅の床面積の10倍を限度として固定資産税の課税標準額が減額されます。
居住部分の割合が2分の1以上の住宅についての課税標準額の算定方法は下表のとおりです。
なお、居住部分が4分の1以上、2分の1未満の場合は算定方法が異なりますので詳しくはお問い合わせください。
| 住宅用地の区分 | 適用面積 | 課税標準額の算出方法 |
| 小規模住宅用地 | 1戸につき200平方メートル以下の部分 | 200平方メートルまでの価格×6分の1 |
| 小規模住宅用地以外の住宅用地 | 1戸につき200平方メートルを超える部分 | 200平方メートルを超える部分の価格×3分の1 |
住宅建替え中の土地に係る特例措置
毎年1月1日時点で住宅が建築中の土地や更地となっている土地は、住宅用地に対する課税標準の特例は適用されません。
例外として、住宅から住宅への建替えで次の全ての要件に該当する場合は、引き続き軽減措置を受けることができます。
なお、この特例を受けるためには申告が必要となります。
適用要件
- 建替え中の土地が、住宅を取り壊した年の1月1日現在において住宅用地であったこと
- 住宅を取り壊した翌年の1月1日現在、建替え中の土地において住宅を建築するための工事に着手していること
- 住宅を取り壊した翌々年の1月1日現在までに完成するものであること
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
- 住宅を取り壊した年の1月1日現在における土地の所有者と、その翌年の1月1日現在における土地の所有者が原則として同一であること
- 取り壊した住宅の所有者と、建替える住宅の建築主が原則として同一であること
申告期限
住宅を取り壊した年の翌年の1月31日まで
申請書のダウンロード
土地の評価替えに伴う税負担の調整措置
税負担の調整措置とは、3年に1度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置です。この措置によって、毎年徐々に評価額に基づく税負担に近づけていくことになります。
この措置に関する詳しい内容については、「税の負担調整措置について」をご確認ください。
新築住宅に対する減額措置
新築された専用住宅、共同住宅及び併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)などの家屋で、次の要件に該当する家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
- 床面積要件
床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の家屋 - 減額される範囲
減額の対象とされるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(住宅部分)だけですので、併用住宅の店舗部分や事務所部分などは減額の対象になりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額の対象に、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル相当分までが減額の対象になります。 - 減額される期間
・一般の住宅(下記以外の住宅)は、新築後3年間
・一般3階建以上の中高層耐火建築物は、新築後5年間
認定長期優良住宅に対する特例措置
認定長期優良住宅を建築した場合、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。(新築住宅に対する減額措置に代えて適用となります。)
- 減額の要件
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けて新築された住宅であること - 減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1に減額します。 - 減額される期間
新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分) - 必要書類
・認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
・認定を受けて新築された住宅であることを証する書類(認定通知書)
住宅の改修工事に対する減額措置
<共通注意事項>
- 改修工事完了後3カ月以内に申告をされなかった場合は減額を適用できません(やむを得ない理由がある場合を除く。)
- 省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行った場合には、減額制度を重複して適用することが出来ます。ただし、耐震改修工事との重複はできません。
- 各改修工事と併せて行ったリフォーム等の費用は適用要件にある自己負担額に含まれません。
- 建築から相当に年数が経過した家屋の場合、この制度により減額される税額が証明書の発行手数料を下回るケースもあります。
証明書の発行や手数料については、証明書の発行主体(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)に直接お問い合わせください。
< 各種減額措置の詳細はコチラ >
耐震改修に対する固定資産の減額措置について(Wordファイル:25.9KB)
バリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置について(Wordファイル:29.2KB)
省エネ改修(熱損失防止改修)に対する固定資産税の減額措置について(Wordファイル:27.7KB)
国土交通省ホームページ(増改築等工事証明書類等)
住宅の耐震改修に対する減額措置
耐震改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3か月以内に税務課資産税係に申告してください。
- 減額の要件
・昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・現行の耐震基準に適合する改修であること
・改修工事費の自己負担額が50万円超であること - 減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額を2分の1に減額 - 減額される期間
耐震改修工事の完了した年の翌年度分 - 必要書類
申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、税務課資産税係窓口に備え付けております。
(1)固定資産税住宅耐震改修減額申告書(Wordファイル:19.1KB)
(2)現行の耐震基準に適合適合した工事であることを証明する書類(増改築等工事証明書、住宅改修証明書又は、住宅性能評価書)
(3)耐震改修工事に係る工事費用の明細及びその支払いが確認できる書類
(4)長期優良住宅認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅に該当する場合)
住宅のバリアフリー改修に対する減額措置
バリアフリー改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3か月以内に税務課資産税係に申告してください。(新築住宅に対する減額措置及び耐震改修に対する減額措置を受けている期間は適用されません。)
- 減額の要件
(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く。)であること
(2)改修工事の自己負担額が一戸当たり50万円超であること
(3)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
(4)次のいずれかの方が居住していること
・65歳以上の方
・要介護または要支援認定を受けている方
・障害のある方
(5)次のいずれかの工事であること
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化 - 減額される範囲
一戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額 - 減額される期間
バリアフリー改修工事の完了した年の翌年度分 - 必要書類
申告には、次の書類が必要です。申告書の様式は、税務課資産税係窓口に備え付けております。
(1)固定資産税バリアフリー改修工事減額申告書(Wordファイル:20.4KB)
(2)納税義務者の住民票の写し(ただし、申請書に納税義務者の個人番号を記入していただいた場合は不要)
(3)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
(4)改修工事箇所の写真または増改築等工事証明書
(5)介護保険の住宅改修及び補助金等を受けていることが確認できる書類(介護保険の住宅改修費及び補助金等を受けている場合のみ)
(6)該当する区分に応じた書類
・65歳以上の方は、住民票の写し
・要介護または要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し
・障害のある方は、身体障害者手帳または療育手帳の写し
住宅の省エネ改修に対する減額措置(熱損失防止工事)
省エネ改修を行った住宅について、次の要件を満たすものは固定資産税の減額を受けることができます。改修工事後3か月以内に税務課資産税係に申告してください。
- 減額の要件
・平成26年4月1日以前に建築した住宅であること(賃貸住宅を除く。)
・改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること - 減額対象工事
・改修工事費の自己負担額が60万円超であること
・窓の断熱改修工事(必須)
・窓と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事 - 減額される範囲
一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1を減額 - 減額される期間
省エネ改修工事の完了した年の翌年度分 - 必要書類
・固定資産税熱損失防止改修工事減額申告書(Wordファイル:20.9KB)
・納税義務者の方の住民票の写し(ただし、申告書に納税義務者の個人番号を記入いただいた場合は不要)
・現行の省エネ基準に適合した工事であることを証明する書類(増改築等工事証明書)
・省エネ改修工事に係る工事費用の明細及びその支払いが確認できる書類
・補助金等を受けていることが確認できる書類(補助金等を受けている場合)
・長期優良住宅認定通知書の写し(改修により認定長期優良住宅に該当する場合)
わがまち特例
地方税法に規定する固定資産税の特例措置の一部に、法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」といい、平成24年度税制改正により導入されております。
利府町では、固定資産税に係る特例率について、利府町町税条例附則第10条の2各号に規定しています。
なお、詳細については次の表を御覧ください。
| 名称 | 根拠 | 取得期限 | 適用期間 | 特例率 |
| 汚水又は廃液の処理施設 | 地方税法附則第15条第2項第1号 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 2分の1 |
| 下水道除害施設 | 地方税法附則第15条第2項第5号 | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 期限なし | 5分の4 |
| 再生可能エネルギー発電設備(太陽光) | 地方税法附則第15条第25項第1号イ(1,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
| 地方税法附則第15条第25項第3号イ(1,000kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 | |
| 再生可能エネルギー発電設備(風力) | 地方税法附則第15条第25項第1号ロ(20kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
| 地方税法附則第15条第25項第3号ロ(20kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 | |
| 再生可能エネルギー発電設備(地熱) | 地方税法附則第15条第25項第1号ハ(1,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
| 地方税法附則第15条第25項第4号ロ(1,000kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | |
| 再生可能エネルギー発電設備(水力) | 地方税法附則第15条第25項第3号ハ(5,000kW以上) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
| 地方税法附則第15条第25項第4号イ(5,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | |
| 再生可能エネルギー発電設備(バイオマス) | 地方税法附則第15条第25項第1号ニ(10,000kW以上20,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 3分の2 |
| 地方税法附則第15条第25項第4号ハ(10,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 2分の1 | |
| 再生可能エネルギー発電設備(木竹・農作物由来バイオマス) | 地方税法附則第15条第25項第2号(10,000kW以上20,000kW未満) | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで | 3年間 | 7分の6 |
| 雨水貯留浸透施設 | 地方税法附則第15条第40項 | 令和3年11月1日から令和9年3月31日まで | 期限なし | 3分の1 |
| 貯留機能保全区域 | 地方税法附則第15条第41項 | 令和4年4月1日から令和10年3月31日まで | 3年間 | 4分の3 |
| サービス付き高齢者向け住宅 | 地方税法附則第15条の8第2項 | 平成27年4月1日から令和9年3月31日まで | 5年間 | 3分の2 |
| 大規模修繕等が行われたマンション | 地方税法附則第15条の9の3第1項 | 令和5年4月1日から令和9年3月31日まで | 1年間 | 3分の1 |
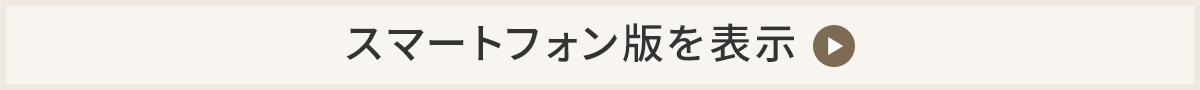





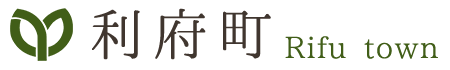
更新日:2025年09月03日